
TANA
Gallery Bookshelf
TOKYO | KANDA
| 110904 | Oyama Enrico Isamu Letter I Know You Don't Really Care, For It 11.09.04 SUN -11.09.25 SUN |
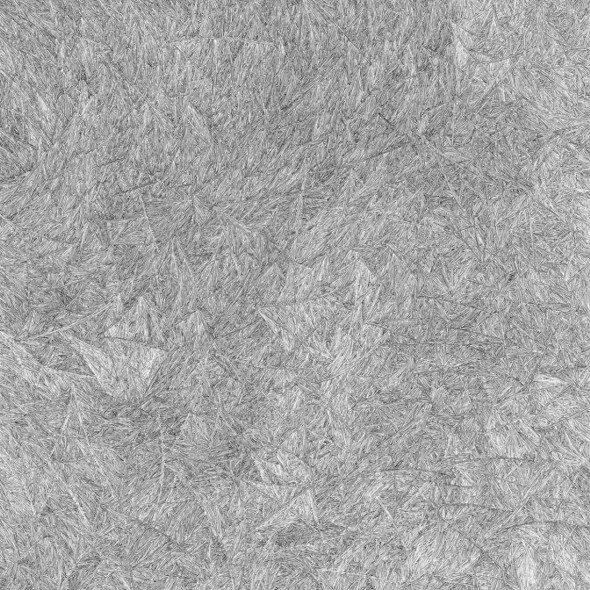
直線、曲線、そして急旋回―大山エンリコイサムは、グラフィティ・レタリングの視覚的イメージをその基礎的な要素にまでいちど解体し、そこから新たに、QTSとよばれる抽象的なモチーフを立ち上げる。形態の自律性と、その自己組織的な広がり・伝搬。もしくは、いくつかの水準において駆動する身体操作(指先・手首・肘・肩・腰)。パターン化された原理はぶれずに、淡々と実行される。とはいえ、壁面、キャンバス、画用紙、時に空間など、さまざまな媒体との摩擦を経験するなかで、QTSはその表情や素材を変化させざるをえない。要するに、作品として残される運動の痕跡=表象はそのつど異なる。ただ、その手前にある運動そのもののロジックは維持されるようだ―でも、本当に?
いずれにせよ棚ガレリは、特異の空間的制限とQTSのあいだに生じる拮抗関係のひとつの痕跡として、大山エンリコイサムの個展「 I Know You Don't Really Care, For it 」を開催する。
Event
Artist Talk & Opening Party
2011.09.04 (Sun)
6pm-
Artist Talk
(in Japanese)
8pm-
Opening Party
(DJ: Oyama Enrico Isamu Letter, Nothto, and TANA)
| Appx |
「I Know You Don't Really Care, For It」展のオープニングでは大山エンリコイサムのこれまでの活動を再訪しながら、彼の作品やプロジェクトに表された思考を追うインタビューを行いました。このオープニングでのインタビューに基づいて、幾度かのメールでのやりとりを経て再構成されたものが以下のインタビューです。
- まずは大山エンリコイサムさん自身について教えてください。
小さい頃から漫画や落書きなど、絵をよくかいていました。親戚に漫画をかくのが得意な人がいたり、テレビゲームも好きだったので、そういう影響も大きかったですね。ただ、その頃は特にアートに大きな関心があったわけではありません。多くの日本の子供のように、漫画やゲームが好きで、ただ落書きをかいていたという程度です。その後、高校生の時にグラフィティというものを知って興味をもちました。僕は東京生まれ東京育ちですが、父親がイタリア人なので16歳から17歳まで一年間イタリアに住んでいて、その頃や日本にもどって少しの間はグラフィティをかいたりしました。周りにグラフィティをやっている人がいなかったので、見よう見まねでストリートに数回かいてみたという感じです。
その後、どちらかというとDJやクラブでイベントをやっている知り合いが多くなってきたので、大学生になってからは自然にクラブでライブ・ペインティングをやるようになりましたね。19歳の時に初めて下北沢のクラブでライブ・ペインティングをして、それがきっかけで東京のクラブ・シーンに関わるようになり、23歳くらいまで恵比寿ミルクを中心に東京のあらゆるクラブでペイントしました。週に2〜3回、年間で100回以上はやっていたかな。もちろん、キャンバスの作品や壁画をかいたりもしましたが、主な活動はライブ・ペインティングでした。その頃に、日本各地で同じような活動をしているペインターに多く出会い、一緒にかいたりして、ライブ・ペインティングを通してネットワークが広がっていきました。2003年から2007年くらいにかけてです。
その後、2007年に美大の大学院にはいったのですが、そこで視野が大きく広がったと思います。自分がそれまで活動してきたクラブやストリート・カルチャーのアート・シーンとは違った、現代美術や美術批評の価値観がありました。最初はなかなかなじめない部分もあったのですが、時間をかけて接しているうちに少しずつ飲みこめてきたんですね。例えば、それまでの自分はファイン・アートとストリート・アートを二項対立で考えてしまう傾向があったのですが、その見方は図式的だったなと思うようになりました。
当たり前のことですが、両方の世界にさまざまな立場や文脈があり、それらは時にとても近く、時にとても遠い。だから、ファインかストリートかというカテゴリーではなく、その両方が重なったり交差したりするような地点から、制作や考えを進めるようになりました。そういった経緯で、現在は自分のなかのいろいろな経験を咀嚼しながら、主に壁画や絵画作品を制作したり、ライブ・ペインティングをしたり、最近はシンポジウムへの参加や評論をかく機会も増えています。
 シンポジウム「ポストグラフィティの開拓線」 パネリスト:荏開津広、大山エンリコイサム、酒井隆史、南後由和、林文浩 旧在日フランス大使館、東京 2009年 撮影:津島岳央 |
- 美大に入る前と、入った後で、ひとつ変化があったということですね。
そうですね。もちろん美大にはいる前にも、さまざまな展覧会を見に行ったり自分なりの勉強はしていましたが、実際に美術の世界で活動している人たちと関わったことがなかったので、外から眺めているという感じで実態がつかめていない部分がありました。「現代美術」という単一のカテゴリーを自分のなかで仮想的に立ちあげて、その内側と外側というふうに二分法で考えてしまうところがあったと思います。美大に入ってから、現代美術をやっている人たちに多く会い、そのような考えは徐々にほぐされていきました。そんなに単純じゃないな、と。ただ、自分のなかの全てがリセットされてしまったというわけではありません。ライブ・ペインティングなどを通して自分のなかで蓄積された経験が、新しい経験に出会って、少しずつ総合的に塗りかえられていっている感じです。
- 少しずつ掘り下げていきたいと思います。ライブ・ペインティングをよくやっていた頃について詳しく教えてください。
ちょうど大学に入ったくらいから少しずつライブ・ペインティングの機会が増えていき、卒業までかなりの数をやりました。一般大に通っていましたが、主にクラブ・シーンで活動していたので、学外に自分のフィールドがあったという感じです。最初の頃は、とにかくクラブで不特定多数の人に自分の作品を見てもらえるのが嬉しかったし、大学では出会えないような色んな人に知り合えたので、ライブ・ペインティングを通してネットワークが広がっていくのが刺激的で、ひたすら数をこなしていきました。やり方としては、たいていクラブの壁に大きな紙を貼って、マーカーやペンキでかくという感じです。ただ、1〜2年そういう活動を続けていくなかで、限界も感じ始めたんですね。クラブのイベントは夜中に5〜6時間続くので、ライブ・ペインティングも時間をかけてゆっくりかく場合が多いのですが、それだとオーディエンスの集中力が散ってしまいがちで、ダンス・ミュージックがメインのクラブではなかなかきちんと見てもらえないし、表現としてもライブでやることの必然性が薄かった。空間的にも時間的にも「クラブ」というフォーマットのなかでやっていた部分があったんです。もっと他の可能性もあるように思い始めました 。
そこで、友人のペインターに声をかけ、ライブ・ペインティングをメインにした「HUOVA(フオーバ)」というイベントを2006年に3回、コンシール・ギャラリー(渋谷)で行なったんです。「HUOVA」は中国語で松明という意味で、中国の血をひく相方の提案で、暗闇のなかの松明の揺らぎのように、即興性を重視したライブ・ペインティングのイベントにしたいという思いがありました。具体的には5人のペインターが5つの壁に順番にライブ・ペインティングをするという内容で、パフォーマンスをひとり20分という時間設定にしました。当時、ライブ・ペインティングをメインにしたイベントは国内でも数えるほどしかなく、ましてや20分という時間制限を設けてパフォーマンス性をコンセプトにしたイベントは例がなかったのですが、多い時で250人くらいのオーディエンスに集まってもらい、注目を集めることはできました。
 「HUOVA」 参加アーティスト:大山エンリコイサム、Kaz、Que Houxo、Sal、JonJon Green、Sense、Mako、山尾光平、LOOT、Rei、わしおともゆき ギャラリー コンシール、東京 2006年(通年で3回開催) |
- ライブ・ペインティングという表現ための独自のフォーマットとして、「HUOVA」など一連のイベントを企画したということですね。
それに加え、もうひとつの狙いとして、ライブ・ペインティングのシーンを可視化させたいと思っていました。いまでこそいろいろなところでライブ・ペインティングをしている人たちは増えましたが、僕が活動を始めた頃は、全国的にも数えるほどしかそういう活動をしている人たちはいなかったんです。ペインター同士のネットワークはあったけど、その全体像がシーンとして見えることが少なかった。「HUOVA」をやることによって、部分的にであれライブ・ペインティングのシーンを提示したいと思ったんです。ただ、実際にやってみて、いろいろとわかったことは多かったです。ひとつには、ライブ・ペインティングと一言でいっても、人によって背景にあるコンテクストや方向性はそれなりに異なっているんですね。美大に行きながらその教育に限界を感じ、学外のクラブでライブ・ペインティングを始めた人もいるし、逆に僕は、クラブでの活動に限界を感じて「HUOVA」をやり、それから美大に入ってさらに視野が広がった。一方にクラブやストリートの文化があり、他方に現代美術や美大教育があり、それらとの距離感や関わり方も人によってさまざまなわけです。
ファイン・アートとかサブカルチャー、ライブ・ペインティングというようにわかりやすくラベリングするのではなく、そういった複数のコンテクストが個々の作家のバランスのなかで交差して、濃淡のある動的な関係性として色んなシーンが重なったりずれたりしているし、それでよいというのが僕の現在の考え方です。これはすごく当たり前のことなのだけれど、個人的にはライブ・ペイテンィングの活動やイベントを企画する経験のなかで、実感としてそう思うようになりました。
- 作品の話に移りたいと思います。大山さんは「Quick Turn Structure(急旋回構造。以下、QTS)」というモチーフを、壁画や絵画など、さまざまなメディアを通して表現していますね。QTSはどういうものなのでしょうか?
「Quick Turn Structure」は初期の頃から一貫してかき続けているモチーフで、グラフィティ・レタリング(Graffiti Lettering)の影響から始まり、ライブ・ペインティングの活動を通して培ってきた独自の造形言語です。初めてグラフィティに興味をもった時、特に文字を崩してかくレタリングの視覚的なインパクトに影響を受けました。僕は本や雑誌を通してグラフィティを知ったので、まずビジュアル的なものとして出会ったのですね。それで、ライブ・ペインティングを始める前に、紙にドローイングとしてレタリングをずっとかいていた時期がありました。その時に素朴に思ったのは、自分が魅力を感じているのはグラフィティ・レタリングの視覚的な造形要素だということです。線と線の重なりあいやずれ、切り返し、断ち落とし、素早いカーブ、それらの組み合わせによる視覚的な効果。だけど、グラフィティのレタリングはふつう、それらの造形要素を横に並んだ文字列へと記号化してしまう。グラフィティはもともと、公共空間に名前をかいて不特定多数の人々に読ませるというものなので、可読性が重要になります。崩してかきながらも、ぎりぎりのところで文字の形を保っているんです。
 高校時代にかきためられたグラフィティ・レタリングのドローイング(一部)。 |
 Quick Turn Structureによる初期ドローイング作品。 左: FFIGURATI #3 紙にデザインペン 297mm × 210mm 2007年 右: FFIGURATI #4 紙にデザインペン 297mm × 210mm 2007年 |
特に「HUOVA」のような即興性の高いイベントを通して、身体の使い方とそこから生まれるラインの躍動感がQTSを発展させていったように思います。ただ、この身体感覚は、ランダムで破壊的なものではなく、むしろQTSの設計的なパターンに密接に結びついているので、アクション・ペインティングのような派手さはありません。例えば、腰と肩を使って黒の細いカーブを勢いよくかき、次は手首か肘を軸にして手をゆっくりスライドさせながら、白の面塗りで黒カーブを削りエッジを出していく、という感じで、スピードの緩急、身体の使用部位、即興的な部分とある程度パターン化された部分のバランスなどを使い分けながら、動的かつ構造的にQTSをかきだしていきます。
このような感覚は、ライブ・ペインティング以外の作品にも共通していますね。壁画ではさらに、都市空間との関係や壁面のテクスチャ、スケール感などが重要になってきますし、キャンバスの場合は時間をかけてかきこむので、細かなところの精度や密度、モチーフとフレームの拮抗関係を意識します。使用する画材もメディアによって異なるし、それによってQTSの表情も変わっていきます。ストリートにかくこと、壁画として壁にかくこと、キャンバスにかくこと、ライブでペインティングすることは、それぞれ多様な制作条件と歴史的コンテクストをもっているので、そういった複数性を横断するなかで、そのつどQTSを変化させつつ表現の幅を広げていくことが制作のヴィジョンのひとつです。
 FFIGURATI #13 木パネルにペンキ、シャープペンシル 910mm × 1110mm |
メッセージと記号という切り口から考えてみましょう。まず、メッセージは一般的に、差出人・宛先・内容・メディアの4つの要素を含んでいる。都市は公共空間なので、メッセージをのせるメディアとして都市を選ぶということは「社会」をその宛先として想定することになります。例えば、街中の落書きは社会に宛てられたメッセージとして機能しえますね。実際に、歴史上の多くの落書きは何かしら社会的なメッセージ性を含んでいます。ひとつの顕著な例としては、1968年以降、パリの五月革命にはじまる世界的な政治・文化の動乱のなかで「メッセージとしての落書き」が多くかかれました。当時、階級やイデオロギー間の闘争という物語を社会はリアルに共有していたので、受け取る側もそのメッセージを理解するためのリテラシーをもっていたわけです。落書きがリアリティのあるメッセージとして成立するための条件が整っていたのですね。
しかし、特に冷戦以降、世界の大都市はコード化された消費の空間へと変容しつつあり、あらゆるものは記号的に機能してしまいます。そこでは、記号による支配に抵抗しようとすればするほど、逆に「反乱」の名のもとに記号化され、骨抜きにされてしまう。東京のような超消費都市では、街頭演説や市民デモのような社会活動も企業広告や禁止の張り紙といったものとごた混ぜになり、資本主義的・管理社会的な記号の風景として見えかねないか、あるいは少なくても、そういったものにリアリティを感じるのが難しくなってきているわけです。そのような状況においては、かつてメッセージとして機能した落書きも記号として消費され、実効力を失ってしまいます。グラフィティが最初に現れた70年代は、まさに都市空間がそのような記号の場へと変貌しはじめた時期でした。
フランスの思想家ジャン・ボードリヤールが「からっぽの記号」と評したように、当時グラフィティがラディカルだったのは、それが単なる名前だったということです。「からっぽの記号」という表現については説明が必要でしょう。歴史的に落書きの多くは「主語+述語(+α)」のようなセンテンス形式になっていて、どんなに取るに足らない内容だとしても状況や意味の読みこみが何かしら可能です。それに対して、名前というのはそもそも恣意的かつ私秘的な記号であり、「主語+述語(+α)」というセンテンス形式のようには意味が読みこめない。特にグラフィティではタグ・ネームとよばれる変名を、たいていは語の視覚的・音声的印象によって新たに自己命名するので、それ自体では意味を欠いた図像でしかありません。落書きがメッセージではなく記号、それも意味に汚染されていない「からっぽの記号」として登場したのですね。
これは、体制にとって新たな脅威であったはずです。なぜなら、豊かな意味をもつ対象を記号化することで矮小化し、骨抜きにしてしまうという高度資本主義の戦略は、あらかじめ記号であり、また矮小化すべき意味すらもたない「からっぽの記号=グラフィティ」を前に、つまづいてしまうからです。そのことによってグラフィティは、記号に正面から抵抗するのではなく、むしろ同じ記号の論理でシステムのなかに入りこみつつ、その意味のつまったネットワークの内側に空白をもちこむことで機能不全をおこすように作用したと言えます。30年以上前のボードリヤールの次の言葉は、たしかに的確でした。
からっぽの記号表現として、都市の(意味が)つまった記号の領域に侵入し、みずからの存在を示すことだけで、それらの記号を解体してしまうグラフィティは、なんの内容も、メッセージももたないからこそ、そういうことができたのであって、このからっぽの状態が、グラフィティに力を与えている。
(ジャン・ボードリヤール「クール・キラー、または記号による反乱」『象徴交換と死』今村仁司+塚原史 訳、ちくま学芸文庫、1996年 )
ここで注目したいのは「みずからの存在を示すことだけで」という言い方です。これは匿名性/顕名性やリテラシーの問題にも重なりますが、ここでは次のことを指摘しておきたい。グラフィティが「からっぽの記号」であるならば、どのようにして「みずからの存在を示す」のか。意味を読みこむためのあらゆるフックが失われているにも関わらず、それはグラフィティ・レタリングのもつ造形言語の視覚的インパクトと、かかれる場の選択によって可能になります。電車の窓からふと外を見ると、スプレー塗料でカラフルにかかれたユニークな文字列が視界に一瞬だけ映りこみ、通り過ぎていってしまうという経験。あるいは、目の前を横切る電車の車体にかかれたそれらとの遭遇。このふたつの要素、つまり視覚的インパクトとその都市空間への配置という要素によって、グラフィティは「からっぽの記号」であるにも関わらず、人々の注意を喚起するわけです。
 電車の車体にかかれたグラフィティ(北イタリア、2009年) 撮影:大山エンリコイサム |
バンクシーに代表される近年の政治的・ゲリラ的なストリートアートの動向は、「からっぽの記号」から「意味のつまった記号」へと逆流していったグラフィティの系譜のなかにあると言ってよいと思います。実際バンクシーらの手法は、都市空間において場がもつ意味の操作や転用をひとつの軸にしているという意味で、50〜60年代にヨーロッパで活動し、その後の文化運動にも大きな影響を与えたシチュアシオニストの着想に近いところがあります。先ほど挙げたグラフィティのふたつの要素のうち、都市空間への配置という要素が特にこの流れへと展開していっていますね。都市でゲリラ的な実践をするというジェスチャーが、社会的・政治的な意味の読みこみを特に誘発するのは当然のことでしょう。
 政治色の強いロンドンのストリートアート。既存の意味を操作・転用することで、そこからアイロニカルなメッセージ性を引き出している。 『STREET ART AND THE WAR ON TERROR』 Edited by Eleanor Mathieson, texts by Xavier A. Tapies, Rebellion Books, 2007. |
先に述べたように、QTSは壁にも、キャンバスにも、ライブでもかかれ、プロダクトに落としこまれることもありますが、そこにあるのは複数のメディアとのあいだのテンポラリーな必然性であり、QTSそのものの必然性ではありません。QTSそのものの必然性はその視覚的な構造にのみあり、それは自己組織的なものなので、特定のメディアにとどまらず、複数のメディアを横断することを欲します。壁(都市空間、建築)、キャンバス(フレーム、平面)、ライブ(時間性、オーディエンス)など、メディアがもつ条件や文脈のなかで、そのつど新しくQTSはかたちづくられていく。その繰り返しのなかで、QTSが少しずつかき換えられていくこともありますが、いきなり別のものに置き換わるということはありません。QTS自体の自律性は保持しつつ、制作の経験のなかで少しずつ変化し、また戻り、表現の幅を広げていくという感じです。QTSとメディアの関係というのは、フリー・エージェント(自由契約)状態のようでもあり、またデラシネ(根無し草)のようなものでもあるのです。
 長者町 壁画プロジェクト(あいちトリエンナーレ2010) コンクリート壁面にスプレー塗料、ラッカー塗料 13m × 15m 長者町、名古屋 2010年 撮影:津島岳央 |
 パリ・コレクションにおけるCOMME des GARÇONSへのコミッション・ワーク(2011年) |
 COMME des GARÇONSランウェイの様子。Quick Turn Structureは14分を過ぎたあたりから約2分ほど現れる。 |
 COMME des GARÇONSオフィスでの制作現場(東京、2011年) 撮影:山森晋平 |
「「LEVEL7」のマグニチュード・ゼロ」 at Real Tokyo
大山エンリコイサム
フランシス・アリスのリズム at 10+1
大山エンリコイサム
- QTSはメディアを横断することによって変化していくとのことですが、その点についてもう少し詳しく聞かせてください。
メディアを横断するといっても、各メディアにあった最適解をそのつど見いだしながら、QTSを要領よく作品に落としこんでいくソリューション思考ではけっしてないことを強調しておきたいと思います。そういうデザイナー的な手つきとはむしろ正反対で、そもそもQTSはかなり強固な自己組織的構造をもっているので即座に変化していくということはありません。これはなかなか説明が難しいのですが、QTSにはQTSの論理があり、メディアにはメディアの論理があるわけで、それが互いにぶつかりあい拮抗しあうなかで、双方をねじりながら作品をつくっていくような感覚です。マニュアルがあるわけではなくつねに手探りなのでうまくいかないこともありますが、そのうまくいかなさのなかから何か奇妙なものが生まれてくることを期待している部分もあります。例えば、最近の平面作品ではグリッド構造を画面に取り入れていて、これはQTSの描線の躍動感を減速させる効果を狙っています。ライブ・ペインティングでは身体の動きからでてくる自由な線の運動を即興的に見せることが多いですが、キャンバス上ではまた別の意図があるのです。
 FFIGURATI #17 キャンバスにジェッソ、スプレー塗料、ラッカー塗料、デザインペン、シャープペンシル 900mm × 900mm 2011年 |
「FFIGURATI」は、「GRAFFITI(グラフィティ)」という単語をねじりつつ、そこにイタリア語の「Figura Ti(英:Figure You=形をつくれ)」というニュアンスを重ねた造語です。2009年に、当時スタジオの一部を改装してつくった展示スペースで小さな個展をした時に展覧会のタイトルとして使い、それ以降、主にQTSをモチーフにしたいくつかの作品タイトルに用いています。QTSそのもののメカニズムはQTS自体に内在していますが、それがさまざまなメディアとの関係のなかで個別の作品として表象される時、それはQTSの運動の痕跡であり、「FFIGURATI」という言葉はその痕跡=表象の水準にあたります。ある種の二層構造だと言ってよいかもしれない。QTS自体は描線運動のメカニズムであり、作品へと直接的に定着することはできません。その運動が制作ごとに一回性の痕跡として、個別の作品へと結実したものが「FFIGURATI」です。
- グラフィティの定義は社会的ポジショナリティ(違法性、あるいは合法だとしても、ある種の反社会性があること)、およびメディア・スペシフィシティ(壁面、路上にかかれること)などに多くを負っています。特定の社会的なポジショナリティやメディアに根を下ろさず、それらを横断して展開するQTSは、単純にグラフィティではないのか、あるいはグラフィティに新たな機動性を与え、その定義を撹拌し、行動の領域を拡大するグラフィティなのでしょうか。
重要な質問だと思います。僕自身は、QTSをグラフィティだとはまったく思っていません。グラフィティは歴史を通してすでに様式化されたひとつの文化形態であり、それはおっしゃるように、許可を得ずにストリートに名前をかくものです。くり返し述べてきた通り、QTSはまた別の論理で駆動しているものなので、それをグラフィティと呼ぶ必要はありません。ただし、まったく無関係ではなく、むしろある仕方で強い関係をもっています。それは、強くねじれた関係でしょう。理論的な水準においても感覚的な水準においても、QTSはそのねじれをバネにしてグラフィティからジャンプし、遠くまで飛ぼうとしている。そのようなものだという気がしています。
- お話ありがとうございました。最後に何かありますか。
先ほど紹介した2009年の個展「FFIGURATI」に関して、研究者/批評家の千葉雅也さんによる寸評がウェブ上に掲載されています。短いですが的確な内容で、このメール・インタビューでかいたことにも通底する部分があると思うので、あわせて読んでもらえるとよいかと思います。ありがとうございました。
「ポスト/パスタ・グラフィティ──大山エンリコイサム「FFIGURATI」展」
千葉雅也
大山エンリコイサム|おおやま・えんりこいさむ
美術家。1983年、イタリア人の父と日本人の母のもと東京に生まれる。慶應義塾大学卒業後、東京芸術大学大学院修了。「Quick Turn Structure(急旋回構造)」という独特のモチーフを軸に、ペインティングやインスタレーション、壁画などの作品を発表する。また現代美術とストリートアートを横断する視点から、論文執筆やシンポジウムへの参加も並行して行なう。2011年秋のパリ・コレクションではCOMME des GARÇONSにアートワークを提供するなど積極的に活動の幅を広げている。主な展示に「あいちトリエンナーレ2010」(名古屋市, 2010)、「Padiglione Italia nel mondo : Biennale di Venezia 2011」(イタリア文化会館東京, 2011)など。共著に『アーキテクチャとクラウド―情報による空間の変容』(ミルグラフ, 2010)、論文に「バンクシーズ・リテラシー――監視の視線から見晴らしのよい視野にむかって」(「ユリイカ」2011年8月号、青土社)など。アジアン・カルチュラル・カウンシル2011年度フェローシップ(ニューヨーク滞在)。
http://www.enricoletter.net
英語版インタビュー
| Current | Archive | About |